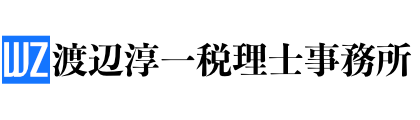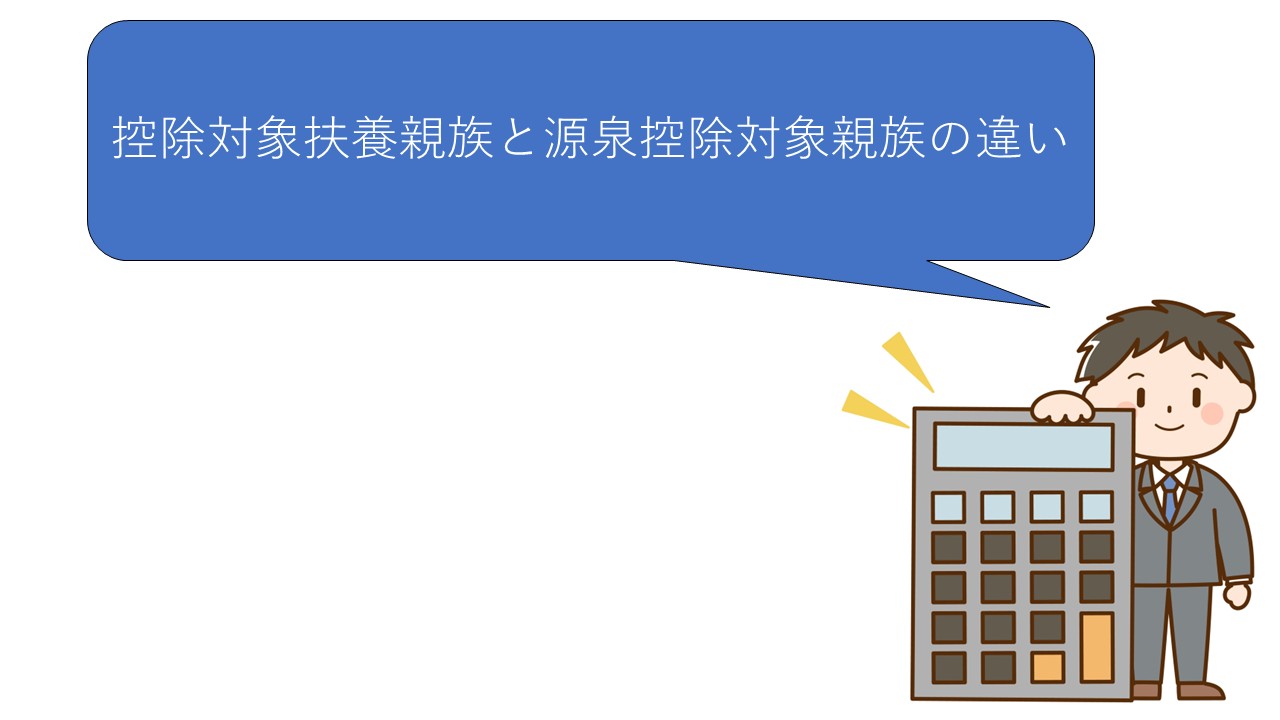税制改正による新しい制度で、聞きなれない用語を疑問に思うことは無いでしょうか。
特に所得税に関しては近年改正が続いており、最も身近な税にもかかわらず勉強する機会もあまりないため分かっているようで分かっていない状況なのかもしれません。
今回は今年の年末調整で登場する用語を中心にその意味を出来るだけ分かりやすく解説したいと思います。
ところで本題に入る前に年末調整で提出する書類には3種類ありますが、一つだけ翌年の書類があることに気づいていましたか。扶養控除等申告書で右上に扶養の扶を〇で囲んだマークがあるため通称マル扶と読んでいる書類ですが、こちらだけ翌年(今年であれば令和7年分ではなく令和8年分)となっています。
これはこの書類を毎年最初の給与支給前に勤務先へ提出する必要があるため、年末調整のタイミングで他の書類(マル配やマル保)と一緒に提出しているためです。
そしてこのマル扶に関する用語について、扶養親族を記載するB欄の箇所が令和7年は「控除対象扶養親族」になっていましたが、令和8年は「源泉控除対象親族」と源泉の2文字が追加され扶養の2文字が削除されています。はたしてこの2つはどう違うのでしょうか。
これまでの控除対象扶養親族は生計を一にする合計所得金額58万円以下の親族で16歳以上の者です。16歳以上ということはすなわち、19歳以上23歳未満の特定扶養親族を含んでいることになります。
一方で新たに定義された源泉控除対象親族は上記の控除対象扶養親族(便宜上①とします)若しくは19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下の者(便宜上②とします)のいずれかとなります。後者の②の方はこの度新設された特定親族に該当します。
源泉控除対象親族のイメージとしてはこれまで通りの控除対象扶養親族(前述①)、特定扶養親族(前述①)、特定親族(前述②)の3パターンがあるということになります。
用語の意義のおさらいですが、特定扶養親族は19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円以下の者(給与収入の場合には123万円以下)で特定親族は19歳以上23歳未満で所得金額が58万円超123万円以下の者(給与収入の場合には188万円以下)を言います。この特定親族のうち所得が100万円以下(給与収入の場合には165万円以下)であれば前述の②に該当し源泉控除対象親族に含まれることになります。
ちなみに同じマル扶のA欄には「源泉控除対象配偶者」を記載することになります。ここは従来通りですが、この箇所も何やら難しい用語になっています。
源泉控除対象配偶者とは、年末調整対象者(1年の合計所得金額の見積額が900万円以下に限る)の配偶者で、1年の合計所得金額が95万円以下(給与収入の場合には160万円以下)の者を言います。(ただし専従者給与の支払を受ける者は除きます)
かっこ書きを端折って要約すれば、給料が160万円以下の奥さん若しくは旦那さんを扶養にする際に記載します。
少しややこしい話になりますが、このマル扶には配偶者の給与収入が160万円を超えれば記載しませんが、160万円を超えても201万6,000円未満であれば配偶者特別控除を受けることが出来るため基礎控除申告書等には配偶者を記載する点ご注意下さい。