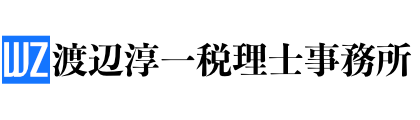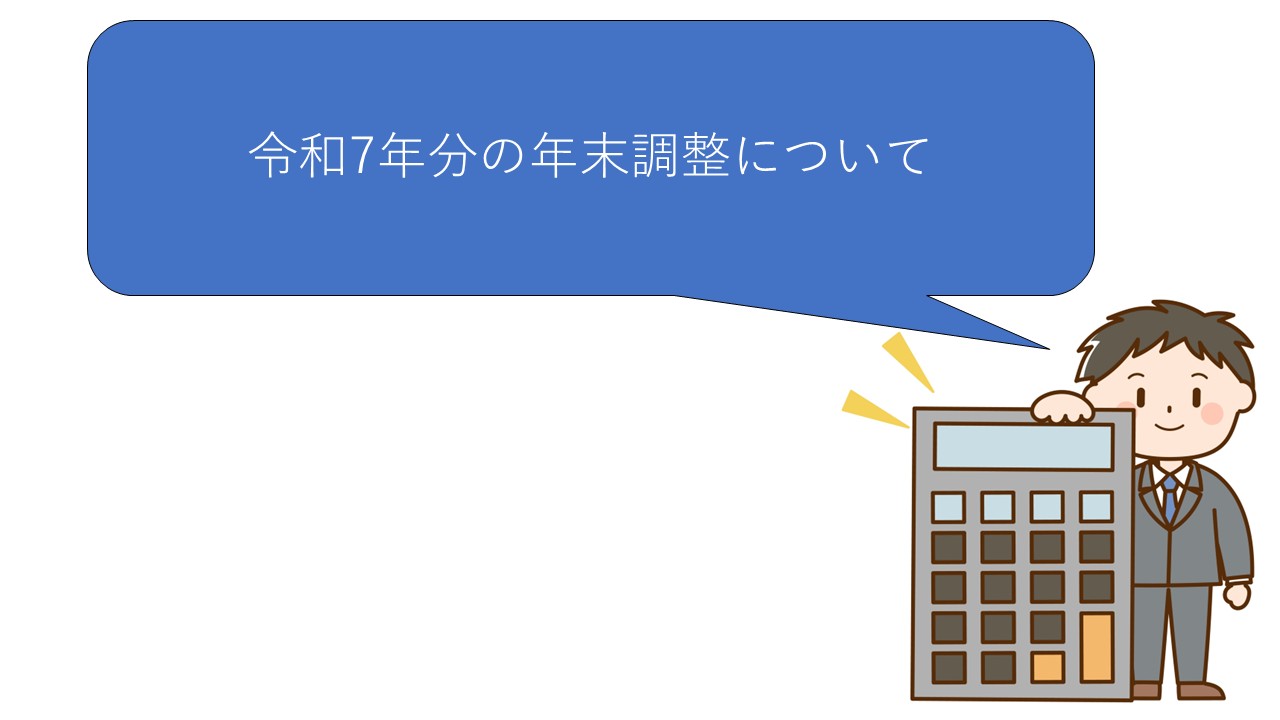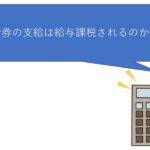まだまだ暑い日が続きますが、国税庁のホームページ上8月末には今年の「年末調整のしかた」が公表されていました。年末調整は所得税に関する改正が続き留意する点が年々増え、それに伴い作業の手間も増えているように感じます。今回は令和7年分の年末調整について取り上げてまいります。
年末調整に関する税制改正で昨年から変わった点が3つあります。
1つ目は今年の12月1日から施行される基礎控除額の引き上げです。所得が2,350万円以下(給与収入のみの場合2,545万円以下)に限りますが、これまでの一律48万円から所得金額に応じて基礎控除額が58万円~95万円へ改正されます。この中には令和7年と8年の2年間限定での加算が含まれますが、現時点では令和9年からまた変わるという点だけ頭の片隅に入れておいてもらえれば十分だと思います。
2つ目は給与所得控除の最低保証額の引き上げです。これまで55万円でしたが、65万円に改正されます。しかしこれは給与の収入金額が190万円以下の場合に限った改正ですので、逆に言えば給与の収入が190万円を超えていればこれまでと何も改正はありません。給与収入額にかかわらずにみんな一律に10万円引き上げで良いのではと思いますが、いわゆる103万円の壁に対応するための改正です。
3つ目は特定親族特別控除の創設です。19歳以上23歳未満の大学生年代の子を扶養する場合、これまではその子の給与収入が123万円を超えれば扶養控除を受けられませんでしたが、改正によりその子の給与収入が123万円を超えても188万円までであれば扶養控除を受けられるようになりました。具体的な控除額としては123万円超150万円以下は63万円で、そこから収入が増えるごとに段階的に控除額は減少していき上限の185万円超188万円以下の場合は3万円の控除になります。
上記の改正点を踏まえたうえで実務上の話をすると、基礎控除と給与所得控除の引き上げはシステムが対応するようになりますが、特定親族特別控除についてはこの改正により新たに扶養控除の対象になる親族がいないかを従業員に確認し、もし該当する場合には従業員から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を受ける必要があります。
以上、今回の年末調整について改正点を中心に取り上げてきましたが、配偶者控除に所得制限が導入されて以降、所得税の計算が段々と難解かつ面倒になっているように思えてなりません。
日本は国民主権ですので、税制を決めるのは国民です。実際は国民が選挙で選んだ政治家が国民を代表して税金に関する法律を定めていますが、果たして国民の意見が反映されているのか、一部の人たちの都合で決められていないか甚だ疑問に感じます。
今年は国民民主党が税制改正の協議に加わり、その模様が報道されることにより税制改正の流れを知る機会が増えて税金に興味を持つ人も少し増えたように感じました。今後さらに生活に直結する税金に興味を持ち意見を持つ人が増えてくれば、きっとより国民の声が反映されるような税制改正になると思います。